 (2006年各種案内)
(2006年各種案内)
日本の教育再建とフランスのエリート教育(2006年12月)
最近、日本でも教育基本法が改正されました。色々な立場の方がおられ、多様な意見が述べられていますが、教育が国家の根幹を形成する点については皆が同意されると思います。
学士会会報で鹿島茂氏の「日本の教育再建」を読みました。少し聞きかじりはしていましたが、フランスのエリート教育は猛烈なのですね。グランド・ゼコールの中でも、エコール・ノルマル、エコール・ポリテクニックと国立行政学院ENAの3校が超エリート校ですが、日本の受験エリートと異なり、生まれた時から「知の貴族」として育てられなければ合格できない。論文試験では、論理展開だけでなく例証が必要で、具体的な例を挙げて自分の教養を見せびらかさないといけない。書き方のルールが決まっていて、それを頭から叩き込まれる。面接では、意地悪な質問やとんでもないところに飛躍した面接官の論理に対しても悠然と持論を展開できなければならないということです。
政治の世界では保守派も社会党、共産党も国民戦線でさえもENAを出た人達が幹部で、大学の先生は皆エコール・ノルマル出身者です。そして、理工系エリートはエコール・ポリテクニック出身です。彼らは国家的な責任を負っているのだというノブレス・オブリージュの意識を身に付けます。
一方、大衆はバカンス法によって金はないけれど暇がある。日本の様に誰もがルイ・ヴィトンを欲しがるというような物質的な欲求はそれほどなくて、土日やバカンスをセカンドハウスで過ごすのを最高の楽しみにしているようです。そして、エリートが国家のグランデザインを考えて、大衆がそれにウイかノンで答える。エリートは大衆に如何にそれが得であるかを説得する技法を学ぶ。大衆はエリートの出したデザインを純粋に損得勘定で選択する。なかなかいいシステムです。だから日本の様にエリートに対する妬みも生じにくい。むしろ、エリートを大衆が利用するシステムなんですね。上手く機能すればどっちも幸せかな。
そこで、日本のエリート教育はという話になり、余裕を持たせつつ、全人格的な教育をし、猛烈に勉強させる、旧制高校のやり方に戻っていくんじゃないかという件になるのは、旧制高校ファンの私でさえも「さすが学士会の夕食会の話だな」と思わず笑ってしまいました。戦後の日本の教育の一番いけないところはエリートが社会で絶対に必要なものだという大前提を否定した事で、一体誰がリーダーになるのかと指摘している点は、ありきたりだけど真実だと思います。
フランスのエリートが必ず引用しなければならない古典はラ・ロシュフコーの「箴言」とラ・フォンテーヌの「寓話」で、カトリック的な「人間はすべて自己愛を根源とする」という性悪説で彼らは論陣を張ります。一方、日本はプロテスタントの潔癖主義、極端に言えばGHQあたりからやってきた倫理主義で論理を展開しようとするから、ひずみが出てきた。(余談ですが、GHQは旧制高校を早く解体したくてたまらなかったそうです。)エリート教育を論ずる時には、すぐに不平等だという人達がいるから、そういう人達を説得できる論理を構築する必要があります。そう、エリートでない我々大衆も得ができるという説得を。
ラ・ロシュフコーの「箴言」とラ・フォンテーヌの「寓話」の岩波文庫版を、私が中学生の頃、福知山で私塾を開かれていた確か東北大学出身の先生から頂きました。その先生の良さを未熟者の私はきちんと見抜けなかったのですが、おそらく月謝以上の書籍を毎月もらっていました。大学の物理や化学の教科書や哲学、倫理学、文学、古典等、今でも書棚に眠っています。彼は凄く学問が好きな、今で言うフリーターだったのでしょうか。裕福そうでは無かったけれども、好きな本に囲まれて楽しげではありました。
バレエpart.1(トウシューズ)(2006年11月)
 バレエ事情に疎い私にはピンと来ませんが、「トウシューズが履ける!」と長女とママがとても喜んでいます。Toe shoes(Pointe
shoes)はWikipediaによると、“誰もが履いて足先で立つことができるわけではなく、バレエシューズで正しい形でバレエが踊れるようになり、ある程度の筋肉がつき、体を引き上げることができるようになるまでは履いて足先で立ったりしてはならないとされる。教師の許可が出されていないのにトウシューズを履いて立つと、怪我をしたり、変な位置に筋肉がついたり、間違った立ち方の癖がついたりする可能性がある。”とあるので、きっと或る程度上達した証だから嬉しいのでしょうね。最終的には努力すれば皆が到達することができるのでしょうが。 バレエ事情に疎い私にはピンと来ませんが、「トウシューズが履ける!」と長女とママがとても喜んでいます。Toe shoes(Pointe
shoes)はWikipediaによると、“誰もが履いて足先で立つことができるわけではなく、バレエシューズで正しい形でバレエが踊れるようになり、ある程度の筋肉がつき、体を引き上げることができるようになるまでは履いて足先で立ったりしてはならないとされる。教師の許可が出されていないのにトウシューズを履いて立つと、怪我をしたり、変な位置に筋肉がついたり、間違った立ち方の癖がついたりする可能性がある。”とあるので、きっと或る程度上達した証だから嬉しいのでしょうね。最終的には努力すれば皆が到達することができるのでしょうが。
若い頃にイタリアでの学会後、妻とミラノに立ち寄った時、折角だからとスカラ座のガレリア席で「白鳥の湖」を観ました。劇場でバレエを観たのは最初でしたが、天井桟敷からでもバレエの美しさ、面白さは何となくわかりました。オペラやバレエが好きで、でも余り裕福でない人でも観劇(感激)できるガレリア席は貴重だと思います。例えば吉田都が大好きなバレリーナの女の子が、自分のお小遣いで観覧するには日本ではお金がかかり過ぎますものね。
ヨイトマケの唄(2006年10月)
日本語俗語辞書によると、ヨイトマケとは「よいとまあけ」という掛け声から転じ、建築で地固めのときに重い槌を上げ下げする労働やその労働をする人のことを言います。ヨイトマケの多くは女性で、稼ぎの少ない夫を持った妻や、夫に先立たれた未亡人が家族を養うためにこの仕事をしました。
「ヨイトマケの唄」は女手一つで自分を育ててくれた亡き母のことを追慕した名曲です。1966年に美輪明宏(当時丸山明宏)が作詞作曲歌唱しましたが、桑田佳祐、泉谷しげる、米良美一、フォーク・クルセダーズ、槇原敬之他にカバーされています。歌詞の中に土方(どかた)という言葉が含まれているので、民放では放送自粛だったそうです。岡林信康の「手紙」「チューリップのアップリケ」、高石友也の「竹田の子守唄」、フォークルの「イムジン河」や陽水の「自己嫌悪」等名曲でありながら放送自粛曲となっている(いた)ものはたくさんあります。
「ヨイトマケの唄」の特に以下の部分は涙ものです。
小学校で ヨイトマケの子供 きたない子供と いじめぬかれて はやされて くやし涙に暮れながら 泣いて帰った道すがら 母ちゃんの働くとこを見た。なぐさめてもらおう 抱いてもらおうと 息をはずませ帰ってはきたが 母ちゃんの姿見たときに 泣いた涙も忘れ果て 帰って行ったよ学校へ 勉強するよと言いながら。
何度か僕も ぐれかけたけど やくざな道は踏まずに済んだ。どんなきれいな唄よりも どんなきれいな声よりも 僕を励ましなぐさめた 母ちゃんの唄こそ世界一。
この子は本当に良い子ですね。でもきっと、本当に偉かったのはお母さんでしょう。環境は人生を左右するものですから、お母さんが貧しく困難な生活に疲れて、息子の生活や進路を狭く規定していたら、こういう風にはいかずにきっとこの子もぐれていたのではないでしょうか。
「ヨイトマケの唄」とは境遇が異なりますが、私の大学の同級生に学費も生活費も遊ぶお金も全部自分で稼いで、それでも余裕を持って学び、遊び、恋愛をしていた奴がいました。周囲にもとても優しく、皆から一目も二目も置かれていました。つまり、ああいう奴が本当に優秀で素晴らしい人間なのでしょう。臨床の医者なんかになるには勿体無いですね。
テニスpart.1(セルフジャッジ)(2006年9月)
ジュニアテニスは夏休みから新年度が始まり、カテゴリーも変わります。(ただし全国レベルの子供たちは全国小学生、全日本ジュニアなどの大会が夏休みに残っています。)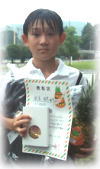 我が長男はママと一緒にツアー選手並みの日程を組み、転戦しました。最大の目標であった京都サマージュニアテニス選手権はベスト4という現実的な結果でした。京都JTCの大会では優勝、準優勝などしました。私はテニスをやっていたというには恥ずかしい程の実力ですから、彼は頑張っている方です。しかし、大阪や兵庫には同学年ですでに昨年度の関西上位に入ったり、全日本ジュニアに出場したりしている選手がいますし、日本中にはこいつ小学生かというほど強い選手がいるようです。まあどんなに上手い選手がいたとしても、フェデラーやナダルを頂点として上には上がいます。そのフェデラーはフレンチ(レッドクレー)で、ナダルはウインブルドン(芝)や全米(ハード)で勝とうと努力しているのですからきりがありません。 我が長男はママと一緒にツアー選手並みの日程を組み、転戦しました。最大の目標であった京都サマージュニアテニス選手権はベスト4という現実的な結果でした。京都JTCの大会では優勝、準優勝などしました。私はテニスをやっていたというには恥ずかしい程の実力ですから、彼は頑張っている方です。しかし、大阪や兵庫には同学年ですでに昨年度の関西上位に入ったり、全日本ジュニアに出場したりしている選手がいますし、日本中にはこいつ小学生かというほど強い選手がいるようです。まあどんなに上手い選手がいたとしても、フェデラーやナダルを頂点として上には上がいます。そのフェデラーはフレンチ(レッドクレー)で、ナダルはウインブルドン(芝)や全米(ハード)で勝とうと努力しているのですからきりがありません。
さて、私が観戦するのは京都か関西の大会ですが、セルフジャッジで行なわれるジュニアの試合に於いて、自分に有利なジャッジをしてしまう子が少なからずいます。率直に言って、兵庫県のジュニアが多くそれも有名クラブ所属です。これでええんかなと思いますが、ここで思い出されるのが舞鶴グリーンテニスクラブでうかがった全日本チャンピオン岩渕聡選手のお父様のお話です。岩渕パパはデビスカップの応援の後に寺内先生のお宅に来られていて、丁寧に喋られる時と関東風(茅ヶ崎風?)のべらんめえ口調の時が混在して面白かったですが、そのお話の一つに、「ジュニア時代は変なジャッジをする子に随分泣かされてきたけど、そういう子はみんな大成しない。審判がついたら、特に接戦のとき勝ちきれない。」というのがありました。将来有為な選手の指導者は、きちんとしたセルフジャッジするように指導して下さいね。そう、あなたのことを言っているんですよ。
岩渕父は、「ジュニアのときみんな速く強いサービスやストロークを打ちたがるけど、筋力がつけばいくらでも打てるようになる。良いフォームで打つ練習はしなければならない。」「試合に負けた時は怒らない方が良い。(本人が一番悔しい。)」「無理な筋トレはいけないけど、走るのは良い。お父さんも一緒に走って下さい。(生活習慣病の改善のためにもね。)」などとも仰っていました。その他色々教えていただきましたが、ジュニアの国際大会(オレンジボウルなど)を目指せというお話は残念ながら参考にできません。
「白痴」黒澤明×原節子part 2(2006年8月)
「白痴」(1951年、松竹)は黒澤明が敬愛するドストエフスキーの小説「白痴」を題材にして舞台を雪と氷の北海道に移して製作された映画です。それにしても凄まじい配役です。黒澤映画とは切っても切れない三船敏郎(この作品の三船は超男前)、対する当時の代表的知性派二枚目役者である森雅之(父は小説家の有島武郎で京大哲学科中退)、伝説的美人女優の原節子(衰えた容姿を見せたくないと隠遁生活に入ったから余計に神話が生まれた)、気の強いわがままなしかし純真な役がぴったりの若き日の久我美子、他に志村喬、東山千栄子、千秋実なども印象的で左卜全まで観ることができます。
こんな映画暗くて(画面も雰囲気もストーリーも)嫌いという人も多々あるでしょうが、最近の映画(洋画、邦画問わず)にはあまり観られない出演者の感情の葛藤(インサイド&アウトサイド)を高く評価する人も多いと思います。
まず、原節子vs久我美子の対決です。小津映画のお嬢さん役を見慣れた目からこの汚れ役の原節子を観ると少々驚きですが、それでも上品さは失わず、fall
intoしてしまいそうなその瞳は健在です。自分の美しさを十分意識した役柄の久我美子もはまり役です。欽司(森)に強く惹かれながら、妙子(原)は欽司(森)と綾子(久我)を結びつけようとする、綾子(久我)も欽司(森)の一番の理解者でありながら妙子(原)に捨てられた香山(千秋)と結婚しようとする。田中康夫風に言えば、“たまらなくアンビバレント”です。(まあ、人は程度の差があるものの皆アンビバレントな存在です。)
三船vs森も他の映画作品同様に対照的で素晴らしい。三船は本当に何をしでかすか分からない男の臭さをプンプンとさせています。森は汚れなき純粋さでもって周囲の人々の心情を反映する男を演じきっています。
東山千栄子もさすがに名演です。ドラマ性を重視する黒澤明と定点観測者の小津安二郎の違いにより、東山千栄子の役柄も規定されるという評論がありましたが、私もそう思います。
ドストエフスキーの「白痴」において、ムイシュキン公爵の純粋無垢な言動は周囲から肯定と否定、賞賛と侮蔑で迎えられます。容姿端麗であるからこそ愛人として生きてきた汚辱にまみれた過去と現在を恨み、純粋な愛情を受け入れることが出来ないナスターシャ。ムイシュキンの親友でありながらナスターシャをめぐる恋敵でもある、粗野で情欲的でしかし可愛いところもあるロゴージン。清純だが、それほど単純でもないアグラーヤ。この不朽の名作をこんな風に映画化するとは黒澤明はやっぱり凄いぜ。
「わが青春に悔なし」黒澤明×原節子part 1(2006年7月)
「わが青春に悔なし」(1946年、東宝)は京大瀧川事件とゾルゲ事件から着想された映画です。京都帝大教授八木原(大河内傳次郎)は法学部教授・瀧川幸辰、野毛(藤田進)は尾崎秀実がモデルだと言われています。1946年という戦前の価値観が180度転換してすぐに、反戦、自由主義、或る意味左翼思想を讃えるような作品が出来たのは、元々の黒澤の思想信条によるものなのでしょうか、それとも戦後流行りの転向によるものなのでしょうか。
原節子は1920年生まれですので、20代半ばの頃の作品になると思いますが、教授のお嬢様からまさに泥まみれの強い女性に変貌していく様は圧巻です。10代の頃は演技の基本が身に付く前に人気が出てしまったために大根女優と言われていたというのが信じられないくらいに強い意志を感じさせる演技です。白黒の暗い場面で汚れにまみれながらもあくまで品位を失わないその姿には魅力を感じます。
戦後に京都や関西以外の地方から京大に入学した人々の中にはこの作品を観て京大に行きたいと思った方が少なからずいるようです。八木原の「自由の裏には厳しい犠牲と責任がある。」という台詞は“自由の京大”好きの琴線に触れます。
糸川(河野秋武)に「野毛は不幸にして道を誤った。」と言われた幸枝(原節子)が「どっちの道が果たして正しかったか、時が裁いてくれるだろうと思います。」と答えたシーンはありきたりの台詞ではあるけれども十分納得させてくれます。“時流に乗るのも人生、抗うのも人生”です。
世間はコピー&ペースト(2006年6月)
島田雅彦の「文芸時評」(朝日新聞夕刊)の最終回はとても良かった。これを読まなければサルであるの「必読書150」でも彼の文章は秀逸ですが。出版社も読者も読みやすく破綻のない文章を求め、「上手にパクリましたね」以外もはや何もいうことはないと。J
popでも流行りの曲はパクリが多いし、各種学会でもマテリアルやメソッドをちょっと変えただけのものが堂々と発表されています。大学受験の分野でも各大学が受験生の資質を見いだそうと努力しているのかも知れませんが、和田秀樹(灘→理科三類)は言うに及ばず、宮台真司(麻布→文科三類)まで受験対策はレトリックのパターンに習熟するだけと語っています。要領の良い人、パターン認識に秀でた人のことを世間では頭が良い人と言うのは真実です。
でもこの模倣行為は全人類がしてきたことです。人間が成長していく過程で、人間性でも、学問でも、芸術でも、スポーツでも、異性関係でも、それが非行(悪さ)でも全部その道の先輩のコピー&ペーストをしてきています。先達の模倣をしながら、その域を超えてしまえば良いのです。本当に創造的な行為や作品はアブノーマルな天才にしかできません。でも、ノーマルな秀才はそのパクリの巧妙さには留意すべきです。盗作ではいけませんからね。パロディーならよいけど。
ここまで書いて、私は島田雅彦の小説を殆ど読んでいないことに気づいたので、舞鶴と福知山のBOOKOFFで7冊彼の作品を買ってきて読みました。勿論、全部105円です。共感できるアブノな部分もあって私は好きですが、彼が言うところの村上春樹の予定調和のファンタジーより島田作品が売れないのはしかたありません。それに、ぎょうさんパクってはりますやん、貴兄も。
アイリッシュセター(2006年5月)
私達が京都から福知山に引っ越しをした時から、いつも一緒だったゴールデンレトリバーのフラッフィーが天寿を全うしました。暫く喪に服しておりましたが、4月23日にアイリッシュセターのシャルルが飛行機に乗って伊丹空港に到着、我が家の一員となりました。当初、グレーハウンド等のサイトハウンドを考慮しましたが、家族に却下されました。大概、私の好みは車でもその他でも家族の趣味と異なり、結局の選択はオーソドックスなものに落ち着きます。
 アイリッシュセターはハートの本では遊び好きの項目が全犬種中トップ、活動性もトップクラス、攻撃性は低い、とここまでは良いのですが、いたずら好きが要注意となります。しかしながら、同じ日本人にも格闘家や芸術家がいるように個体差があるでしょうから、一概には言えません。ゴールデンレトリバーより訓練や飼育に苦労しそうではあります。 アイリッシュセターはハートの本では遊び好きの項目が全犬種中トップ、活動性もトップクラス、攻撃性は低い、とここまでは良いのですが、いたずら好きが要注意となります。しかしながら、同じ日本人にも格闘家や芸術家がいるように個体差があるでしょうから、一概には言えません。ゴールデンレトリバーより訓練や飼育に苦労しそうではあります。
大昔、父がハンティングをしていた頃、ガンドッグ(イングリッシュポインター、イングリッシュセター)がいましたが、私が子供の頃でしたのでどんな犬だったか忘れてしまっています。シャルルは狩猟に於けるセットというこの犬本来の目的に使われることは無いですが、子犬の今でも鳥には敏感に反応しますから、鳥猟犬としての血は流れているのでしょう。とてもかわいいです。
本屋さん(2006年4月)
先日、西のカリスマ書店、本のセレクトショップと呼ばれる恵文社一乗寺店へ行ってきました。そのセレクトは評判通り面白くて、京都造形芸術大学(かつての芸短)の学生さんや先生向けか、芸術・建築関係の書籍があったり、漫画のコーナーでは懐かしい大島弓子や萩尾望都の作品があったり、文学や哲学の棚でもアカデミックミーハーの心をくすぐる仕掛けがあります。
ウィトゲンシュタイン関連、九鬼周造つながり、村上春樹ワールド、大瀧詠一とナイアガラの本を私は買い、まさにミーハー炸裂ですね。
まあでも、これくらいで流行りペイできるなら、ロケーションを考慮すれば他でもできるかなと素人は思います。私は、1)京大生協(ルネ)、2)Amazon(新聞雑誌の書評を鵜呑みにして買うと失敗も多い)、3)ジュンク堂京都店(慣れているので本を探しやすい)、4)アビックス福知山店(福知山唯一の総合書店。開業当時はもっと品揃えが良かったが、今でも地域規模を考えれば悪くない。西田幾多郎でもユングでもフロイトでも入門書なら手に入ります。)、5)アスカ(舞鶴グリーンテニスクラブの近く)の順に利用しています。
もとより、書店・本屋さんは地域の住民の民度を反映します。商売ですから、売れない本は普通置かれないでしょう。しかし田舎町だからといって、アカデミックなものやファッショナブルな書籍、芸術関係の本が売れないかと言うとそうでもないことを大学学部の大先輩に聞きました。また、その書店のディスプレイや揃えられる内容は経営者や店長の知性や哲学や性格を描出します。店舗面積が大きすぎないで、なおかつ自分の読みたい本が揃っている本屋さんが最高です。
東京神田神保町界隈は本好きには(本格派にもミーハーにも)たまらないですし、大学時代最も利用した駸々堂の倒産、京大前のナカニシヤ書店の店舗撤退等は寂しいものです。
開業医は勉強不足か?(2006年3月)
大学医学部の同窓会にヒエラルキーがあるとしたら、母校の学長、医学部長、教授、他学旧帝大医学部教授、国立大学医学部教授・・・・・ときて最下位は確実に開業医です。(他に衆議院議員や官僚、プロボクサー、僧侶、棋士もいますが。)
大学や一般病院の勤務医ならば、色々な情報は入るし、新しい技術も習得しなければ勤まらないでしょう。一方、開業医は開業した時点での技術、知識で一生過ごそうと思えば過ごせると言えます。
では、開業医は勉強不足でしょうか?私はきちんと勉強している人の方がずっと多いと最近思います。産婦人科医会のメーリングリストや各種サイト、掲示板等を拝見すると、開業医や勤務医の方々の示唆に富むお話には勉強させられますし、実際に診療の参考にさせてもらっています。周囲を見渡すと他科の医師も同様に良く勉強されている方が多数と思います。
ただ、例外的な勉強不足の医師は目立ってしまい、町医者(開業医)は勤務医より劣っていると一般の人から思われるのは残念な事です。
当世キャンパス事情(2006年2月)
私は今でも大学キャンパスへ行くのが好きです。この間東京に行った時には、慶應(三田、信濃町)、東大(本郷)を訪れました。京大キャンパスでは、西部のBOOKセンタールネで書籍のまとめ買い(と言っても殆ど他愛のないものですが)、本部の中央食堂で安上がりなランチ、図書館のメディア・コモンでCDを聴くなどします。京大キャンパスは私の学生時代とは比べ物にならないくらい綺麗で、建物も立派になっています。色々なメッセージを掲げた看板は存在するものの目立たなくなり、政治的主張で溢れていた汚いトイレは今では清潔なシャワートイレに変わっています。現在の方が良いような気もするし、ちょっと寂しい気もします。残念なことに折田先生像は総人地下に撤収されていますが、また七変化を観てみたいものです。
京大アメリカンフットボール部の事件が起こりましたが、基本的に個人的な事だと思います。それにしても、新聞、雑誌に掲載されたこの事件に対する評論は的外れなものが多かったですね。唯一、クラブ在籍中と退部後の環境の変化に適応できなかったのではという意見だけがまともでした。ギャングスターズは昔から学内でスター気取りだとか、将来を嘱望されたクォーターバックの自殺とか色々とありましたが、それなりの実績と名声を残したものには毀誉褒貶はつきものです。未熟な若者がちやほやされて舞い上がるのもよくあることです。しかし、男女の性や考えが異なるというのは、高校生や大学生でも知っておいた方が良いでしょう。おそらく軽い気持ちで行った行為が相手を深く傷つけ、自分の有為な前途を崩壊させてしまったのですから。(君に言われたくないとの声がまた聞こえますが。)
同志社の学生の事件も世間や大学関係者、学習塾関係者に衝撃を与えました。同志社法学部出身の妻は、「法学部だけであんなにたくさん学生がいるんだもの、正常でない人も紛れ込むでしょう」、ついでにレイザーラモンHGは単位も落とさず、講義にもきちんと出席した学生だったと聞いて、「商学部で真面目に勉強するなんて、やっぱり変わっているのね」とさらりと語っていました。同志社の自由な学風に対しては私たちも深い敬愛の念を持っています。更なる発展を期待しています。特に同志社スポーツもっと頑張って!
分娩時の浣腸、剃毛、会陰切開について(2006年1月)
浣腸、剃毛、会陰切開は、医療施設における分娩の3大非人道的処置と言われているようです。
私が研修医になった頃は、分娩入院時の浣腸は必須の処置で、施行していなければ担当助産師、研修医は怒られたものです。しかし、最近ではWHO勧告で「ルーチンの浣腸施行は産婦を心理的に非日常的な状態にさせて産婦の分娩における主体性を損なう。明らかに有害で効果が無いので止めるべきこと。」とされています。流行のEBMでも分娩所要時間、感染症に対して浣腸の有効性は認められていません。長期間排便が無いとか、産婦が希望するとかがなければ、浣腸はしない方が良いでしょう。
外陰部の剃毛もWHO勧告で「止めるべきこと」とされていますし、却って剃毛した傷よりの感染が指摘されているので、施行しない方が良いでしょう。
会陰切開については、非人道的処置で施行しない方が良いとばかりは言えないようです。当院では平成17年1月よりできるだけ会陰切開をしない方針を打ち立てています。結果として、当然のことながら会陰縫合が不必要な方が増えました。切開創と比べて自然裂傷がぎざぎざできれいに治りにくいということもありませんでした。しかし、出口での分娩時間を短くする、直腸に達する裂傷を防ぐという本来の利点を生かすべき時は、会陰切開をすべきであると考えられます。
|


